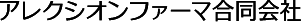知っておきたい社会保障制度
⽇本には、トランスサイレチン型⼼アミロイドーシスの患者さんを含め、難病患者さんが安⼼して療養できるようにさまざまな⽀援制度があり、各地域に患者さんとご家族を⽀える専⾨スタッフがいます。
どのような制度があるのかを知り、専⾨スタッフに相談しながら安⼼できる療養⽣活をつくっていきましょう。
⽀援制度や⽣活に関する相談先
各地域には、難病患者さんとご家族が安⼼して療養し、⽣活できるよう⽀援するさまざまな専⾨スタッフがいます。病気や治療、医療費などの経済的負担に関する悩みはもちろんのこと、病気との向き合い⽅やご家族との関わり⽅など気持ちの⾯での悩みについても、⼀⼈で抱え込まずに相談してみましょう。
医療機関の相談窓⼝
病院には、医師や看護師のほかにも、患者さんやご家族をサポートする専⾨職がいます。中でも、医療ソーシャルワーカーは、社会保障制度に関する専⾨知識をもち、患者さんの医療費や⽣活費、⽇常⽣活の不安、仕事や家族関係の悩みなどを聞きながら制度についての情報を提供し、必要に応じて地域の機関やサービスにつなげてくれます。病院内にある「患者相談室」、「医療福祉相談室」、「地域連携室」(施設により、名称は異なります)などを気軽に訪ねてみましょう。
「脳卒中‧⼼臓病総合⽀援センター」の患者さん相談窓⼝
医療機関によっては、国や都道府県、都道府県内の病院‧診療所と連携し、⼼臓病の患者さんやご家族に対して、病気そのものだけでなく、リハビリや⽇常⽣活のアドバイス、お悩み相談、病気の情報提供など様々な⾯から⽀援する「脳卒中‧⼼臓病総合⽀援センター」を開設しているところもあります。
市区町村の役所窓⼝
市区町村の福祉課では、さまざまな社会保障制度の相談や申請を受け付けています。地域によって担当課の名称が異なっていたり、保健所が窓⼝になっている制度もあるため、⽬的を伝えて担当の窓⼝へつないでもらいましょう。
保健所
主に保健師が中⼼となって、難病患者さんの療養相談⽀援を⾏っています。医療費助成申請で保健所を訪れたり、地域の保健所に電話したときなどに、患者さんの相談内容に応じてさまざまな情報の提供や、適切な相談先の紹介をしています。
難病相談⽀援センター
難病患者さんやご家族などからの療養⽣活に関する相談に応じて、必要な情報の提供や助⾔などをしてくれる⽀援施設として、各都道府県や指定都市に設置されています。難病相談⽀援員や、ほかの患者さんとご家族(ピア相談員)に相談することができたり、専⾨医などによる相談会や講演会が開催されたりします。⾯談による相談だけでなく、電話での相談も可能です。
主な⽀援内容
- 電話、⾯談などによる療養⽣活上および⽇常⽣活上の相談や、各種公的⼿続きなどの相談⽀援
- 難病患者さんの⾃主的な活動などに対する⽀援
- 難病患者さんが適切な就労⽀援サービスが受けられるよう関係機関(ハローワーク、障害者職業センター、就業‧⽣活⽀援センターなど)との連携による⽀援
- 患者団体の紹介など
- 参考
- 各地域の難病相談⽀援センターについては、難病情報センターのサイト内「都道府県‧指定都市難病相談⽀援センター⼀覧」ページをご参照ください。
難病診療連携コーディネーター‧難病診療カウンセラー
難病患者さんに合った医療を提供できるように、難病患者さんとそのご家族が安⼼して治療が受けられるように、関係機関との相談や紹介などを⾏います。本コーディネーターおよびカウンセラーは、各都道府県の難病診療連携拠点病院に在籍しています。難病患者さんやそのご家族、難病が疑われながらも診断がつかない患者さんがいる病院からの相談に応じたりします。
- 参考:
- 鈴⽊豊, 他(編). 医療福祉サービスガイドブック2024年度版. 医学書院;
2024,p.162-165.
⼩川⼀枝,他.難病の保健師研修テキスト(基礎編).(2025年2⽉確認)
監修(五⼗⾳順):
信州⼤学医学部 循環器内科 教授
信州⼤学医学部附属病院 脳卒中‧⼼臓病等総合⽀援センター センター⻑
桑原 宏⼀郎 先⽣
信州⼤学医学部 脳神経内科、リウマチ‧膠原病内科 教授
信州⼤学医学部附属病院 信州診療連携センター センター⻑
関島 良樹 先⽣